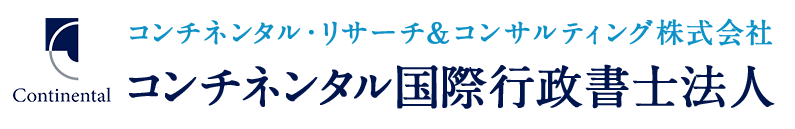すべての士業にある“におい”──見えないブランディング
すべての士業にある“におい”──見えないブランディング
士業とは、法務、会計、労務、税務など、専門的な知識と資格をもとにサービスを提供する職業群を指します。弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士などがその代表です。
これらの職業は、国家資格という制度化された文化資本を有し、専門性と信頼性によって顧客の問題を解決していきます。しかし、制度的信用だけでは、なぜ「この先生に頼みたい」と思われるのかを説明するには不十分です。士業には“におい”のような、非言語的・非論理的な選好の要素が常に付きまとっています。
なぜ説明できない「好き・嫌い」があるのか
顧客が士業を選ぶとき、「有資格者であるか」「料金が明確か」「専門分野が一致しているか」など、ロジカルな判断軸を持って比較するはずです。しかし現実には、「この先生、なんとなく信頼できそう」「ちょっと怖そうでやめておこう」といった感覚的な印象が意思決定を左右します。
これは「第一印象バイアス(first impression bias)」や「ラポール形成(rapport building)」に関係しています。さらに言えば、ブルデューのいう“身体化された文化資本”──すなわち、言葉遣い、服装、雰囲気、イントネーション、しぐさなどが“におい”として顧客に伝わっているのです。
“におい”はどこから発せられるのか
士業が持つ“におい”とは、次のような要素の複合体です:
- 言葉のテンポや抑揚:「早口でまくしたてる」「落ち着いてゆっくり話す」
- 表情と視線:「笑顔が少ない」「優しいまなざし」
- 服装のトーン:「黒を基調とした威厳のあるスーツ」「淡色でやわらかな印象」
- 資料や名刺の質感:「高級紙に活版印刷」「光沢紙にイラスト付き」
- Webサイトのデザイン:「明朝体と白背景」「ポップな配色とゴシック体」
これらは論理的には説明できないけれど、受け手に確実に“印象”を与えています。例えるなら、香水の香りや料理の湯気と同じく、「その場にいなくても残る」ブランディングなのです。
顧客は“におい”で選んでいる
たとえば、専門性がほぼ同じ二人の行政書士がいたとします。一人は東大法学部卒・外資系企業出身で、サイトは理路整然とし、写真も証明写真のように固め。もう一人は専門学校卒・街の事務所で、サイトは手作り感があり、笑顔の写真が多い。
どちらが「優れている」かではなく、どちらの“におい”が自分に合うかで、顧客は判断します。実際、前者にはグローバル企業勤務者が、後者には地域住民やシングルマザーが相談に訪れることが多くなります。
つまり、士業が発する“におい”が「顧客の文化資本」と共鳴するかどうかが、選ばれる理由なのです。
自分の“におい”を意識して設計する
この“におい”は偶然に生じるのではなく、意識的に設計・発信することができます。
- 自分が心地よいと感じる言葉・色・空間を使う:それはそのまま顧客が感じ取る“におい”になります。
- 自分の文化資本に忠実でいる:無理にウケを狙うより、誠実に「自分らしさ」を出すほうが、結果的に共鳴率は高まります。
- 「誰に響かせたいか」を定義する:相手の“嗅覚”に合ったにおいを調合するイメージです。
“におい”は変えられるのか?
もちろん、ブランディングは進化します。若い士業が年齢を重ねて落ち着いた雰囲気になるように、話し方や服装、発信内容は変化します。ただし、“におい”が混ざると、かえって違和感を持たれることもあります。
たとえば、ポップなサイトに突然「憲法○条により~」と書き出すと、「なんか違う」と思われるかもしれません。
だからこそ、“におい”は常に点検し、一貫性を保ちながら微調整を重ねることが大切です。
次章では、こうした“におい”をより実務的な視点で、発信戦略や導線設計にどう落とし込むかを掘り下げていきます。
コラム:ラーメン日高屋と“感ピューター”経営──現場の“におい”を読むブランディング
「すべての出店予定地は、私が必ず自分の足で見に行きます」。
これは、ラーメンチェーン「日高屋」を展開するハイデイ日高の創業者・神田正会長が、自身の出店戦略について語った言葉です。2024年現在で400店舗以上を展開する中でも、出店候補地は必ず自ら歩き、自らの感覚で判断するといいます。
もちろん、立地選定には統計データや通行量などのマーケティング要素も加味されているでしょう。しかし神田会長が重視するのは、いわゆる「数字」ではなく、「現場の空気」「におい」「温度感」といった、感覚的な判断軸です。
こうした姿勢は、いわば「感ピューター」とでも呼べる直観的経営であり、データ偏重の時代においては逆説的な価値を放っています。
実は、士業のマーケティングやブランディングにおいても、こうした“においを読む力”は極めて重要です。
データでは見えない顧客とのマッチング
士業の世界でも「立地」に相当する要素があります。たとえば事務所の場所、Webサイトのデザイン、プロフィール写真、問い合わせフォームの設計、SNSでの言葉遣いなどは、すべて“出会いの場”であり、そこに漂う“におい”が顧客に印象を与えます。
たとえWebサイトのSEO対策が万全でも、「この雰囲気は合わないな」と感じられたら、顧客はページを閉じてしまいます。逆に、検索順位が低くても、「この先生、なんだか安心できる」と思ってもらえれば、問い合わせにつながることがあります。
これは、日高屋が「人通りが多い」というだけではなく、「ここには温かみのある客層が集まっている」といった“質”を読み取る感性に通じています。
士業にも“においの合う”顧客がいる
神田会長は、繁盛店をつくるのではなく「客の呼吸に合った店」をつくるのだと述べています。
この考え方は、士業にもそのまま当てはまります。すべての人に広く薄くウケようとするのではなく、「この層にだけ深く刺さる」という設計こそが、信頼に基づく関係を築く鍵になります。
「価格を比較して依頼する層」と「誰に依頼するかで選ぶ層」は、まったく異なる文化資本を持っています。そして、後者の層は“におい”で選びます。
神田会長が「ビルの色調が冷たい」「人の流れに生活感がない」と判断するように、顧客も「文章が堅苦しい」「声が強すぎる」「説明が曖昧」といった印象から、無意識のうちに「この先生は違うかもしれない」と感じ取っています。
感性を信じることの意味
現代のマーケティングは、ロジックや数字を重視する傾向があります。もちろん、それらも必要です。しかし、士業のように「誰に相談するか」が極めて重要になるサービスにおいては、“においの設計”が集客の成否を左右する場面も少なくありません。
顧客は、「実績○件」「報酬○円」ではなく、「この先生は誠実そう」「この人の言葉は伝わりやすい」といった、直感的で非言語的な評価軸で選んでいることが多いのです。
日高屋のように、出店地を自ら歩き、現場の空気を感じ取るように、士業もまた、自身の発信や接客、資料、メール文面などにどのような“におい”が漂っているかを、繊細に感じ取る必要があります。
士業こそ“感ピューター”であれ
士業の世界では、ロジックが重視される場面が多いため、自らの感性や直感を軽視しがちです。しかし、最終的に依頼をするかどうかを決めるのは、依頼者の“気分”や“雰囲気”に対する共鳴であることが多いのです。
だからこそ、数字では測れない現場感覚──つまり“においを読む力”を信じて、そこに手間を惜しまず、研ぎ澄ましていく必要があります。
士業が日高屋のような「感ピューター経営」を実践することで、顧客との接点における“においの一致”を高め、選ばれる存在へと近づいていくはずです。
── においは見えません。しかし、人の心は、それに最も敏感なのです。