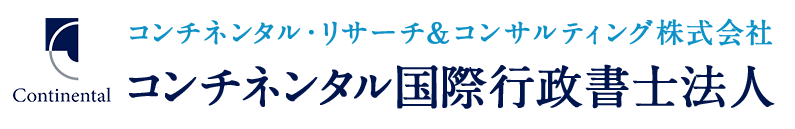外国人雇用ガイド|技術・人文知識・国際業務ビザの取得方法
外国人従業員の雇用ガイド
就労ビザ:技術・人文知識・国際業務ビザ(ぎじんこく)
技術・人文知識・国際業務ビザ(通称:技人国ビザ)は、日本で外国人が企業に就労する際に最も一般的な在留資格です。「就労ビザ」というのは、この技術・人文知識・国際業務ビザを指すことが大半です。このビザは、学術的な素養や外国文化に基づいた専門的な技術や知識を持つ外国人に付与されるもので、いわゆる「ホワイトカラー職種」を対象としています。
技術・人文知識・国際業務ビザの主な条件
技人国ビザを取得するためには、以下の条件を満たす必要があります:
- 学術的な専門知識や外国人ならではの感受性を必要とする職務であること
- 関連する学歴や職歴を有していること
- 日本人と同等以上の給料が支払われていること
- 雇用契約が日本の企業と締結されていること
- 会社の経営状態が安定していること
- 外国人本人が法令を遵守していること
これらの条件をクリアすることで、技術・人文知識・国際業務ビザが取得可能です。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く)。
技術・人文知識・国際業務の対象となる職種と注意点
技術・人文知識・国際業務ビザが適用されるのは、技術者やITエンジニア、金融専門職、翻訳通訳、マーケティング職などの専門的な職種です。一方で、飲食業や小売業、コンビニスタッフ、ホテル業などの肉体労働や単純作業は、このビザの対象にはなりません。
ポイント:飲食業などの業種でも、本社スタッフとしての企画やマーケティング業務であれば、技人国ビザが適用される場合もあります。入国管理局は、職務の実質的な内容を重視し、職務に十分な業務量があるかを確認します。


飲食店・レストラン、インバウンド・観光関連業種、
介護施設、外国料理店のコック、外国弁護士・公認会計士等、金型製造、教師(小学校・中学校・高等学校等)、金融機関、建設業、小売・販売業、コンビニ、
障害者施設、スポーツ指導者、スポーツ選手、
タクシードライバー、デザイン/マーケティング関連業、電気工事業、
バイリンガル・スタッフ(翻訳通訳)、美容室、保育園、貿易業、ホテル・旅館業、企業グループ内の転勤(外国子会社→日本の親会社、外国親会社→日本の子会社等)
技術・人文知識・国際業務(ぎじんこく)の要件
技術・人文知識・国際業務の在留資格の取得には以下の6つの要件を満たす必要があります。
要件
①学術的な専門知識・外国人としての感受性等の必要な職務であること
②職務に関連する学歴又は職歴を有していること
③日本人と同等額以上の給料が支払われること
④会社と外国人の間で雇用契約等の契約が結ばれていること
⑤雇用する会社の経営状態が安定的であること
⑥外国人が法令を遵守し犯罪等を起こしていないこと

(1)学術的な専門知識や外国人ならではの感受性等が必要な職務であること
技人国では、学術的な専門知識や外国人ならではの感受性が一定以上必要な職種(職務内容)にしか認められていません(=入国管理局がいわゆる単純労働とみなす職種では認められません)。これらは職務内容の実態で判断されます。
十分な業務量が必要
求められている専門的に知識や素養が必要な職務は、十分な業務量が確保されているか否かです。例えば、「商学部で会計学」を専攻した留学生を「経理財務」の職種で採用しようとする場、経理財務の仕事を「主たる仕事」として十分な業務量が有ることが必要です。
例えば、全体の仕事の中で、飲食店の調理場の仕事が8割、経理部での会計記帳の仕事が2割では経理財務の職務に十分な業務量があるとは認められず、在留資格の許可はおりません。入国管理局からは主たる職務は、飲食店のホール係の単純労働であるとみなされます。
研修計画とキャリアプラン
また、行おうとする職種に技人国に該当しない業務が含まれる場合であっても、それが入社当初に行われる研修の一環であって、今後、技人国に該当する業務を行う上で必ず必要となるものであり、日本人についても入社当初は同様の研修に従事するといった場合には、あらかじめ具体的な研修計画等を提出することにより、技術・人文知識・国際業務の在留資格が認められる場合があります。ただし、例えば、ホテルに就職する場合、研修と称して長期にわたって、専らレストランでの配膳や客室の清掃などの技人国に該当しない業務に従事するといった場合には許容されません(入国管理局ガイドライン)。
なお、総合職で採用して、採用後に部署移動があり、職務内容が変わる場合は注意してください。
(2)職務に関連する学歴・職歴
従事する予定の職務に関連する以下の学歴、または実務経験年数が必要になります(上陸基準省令より)。

学歴
大学卒業またはそれと同等以上の教育
国内・海外の大学院・大学・短期大学・高等専門学校(高専)が含まれます。
入国管理局の審査では、学位を取得していることと専攻内容と職務の関連性を大学等の卒業証明書や成績証明書をもとに確認します。なお、外国の大学等の中には、大学と認められない場合があります。(ご参考:外国の短大や3年制大学の卒業生を採用する場合)
大学等での専攻科目と従事する業務は関連していれば良いため、一致していることまでは求められません(関連性の審査が緩やかです)。
専門学校
日本の専門学校(専門士)のみが対象となります。専門学校の卒業者は大学等の卒業者よりも「専門学校での修得科目」と「従事しようとする業務」との関連性を厳しく審査されます(関連性の審査が厳しい)。
実務経験(あまりない)
- 技術・人文知識に関連する職務の場合:10年以上の実務経験
- 外国人ならではの思想・感受性に関連する国際業務:3年以上の実務経験(大学を卒業した人が翻訳・通訳・語学指導をする場合は実務経験不問)
10年以上の実務経験が必要な場合
最終学歴が高校卒業の場合など、職務に関係のある大学等または専門学校の卒業をしていない場合には、技術・人文知識に関連する10年以上の実務経験が必要です(上陸基準省令)。
実務経験の証明は、過去に勤めた会社での在籍証明書などの書面を証拠書類として立証する必要があるため、円満退社ではないなど、それらの書類を取得できない場合には、実務経験年数が証明できず、在留資格が認められない場合があります。客観的証拠が必要です。
3年以上の実務経験
外国人ならではの思想や感受性が必要とされる国際業務(広報・宣伝・海外取引・服飾デザイン・インテリアデザイン・商品開発)であれば3年以上の実務経験で認められます。
なお、大学を卒業した外国人が翻訳・通訳・語学指導をする場合は実務経験不問であることはポイントです。例えば、美術やスポーツ体育を専攻した大卒者であっても、翻訳や通訳、語学学校の教師であれば実務経験なしで従事することができます。
(3)給料の水準
雇用主の他の日本人の従業員と同等以上の水準の給料を支払う必要があります。日本語能力が低い、などの事情も考えられますが、日本人よりも給料を低く設定することは認められません。
大卒新卒者であれば、その会社の日本人の大卒新卒者と同等として簡単ですが、専門職や研究職などでの中途採用する場合、学歴や職歴、ポストによっても給与水準は異なるため、その会社の給与テーブルや他の職員の給与額を参考にします。
なお、給料の水準は、賞与(ボーナス)などを含めた1年間従事した場合に受ける報酬を12分の1として計算します。この場合、報酬とは「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」 をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除きます。)は含みません(ガイドライン)。
(4)会社と外国人の間で雇用契約等の契約があること
「日本の雇用主と外国人本人との間」で、雇用契約等の「契約」があることが必要です。外国に在る企業等と直接契約している場合は技人国の対象となりません。企業が契約する場合に加えて、個人事業主が外国人を雇用する場合も含まれます。雇用契約の他にも派遣契約やフリーランスとしてのいわゆる業務委託契約なども含まれますが、特定の会社との契約が継続的に見込まれることが前提になります。
※外国の企業等との直接契約、または、フリーランスなどで不特定多数の企業等と単発契約を結ぶ場合は経営管理ビザに該当します。
既に就職が決まっていることの証明として、雇用契約書や内定通知書等を入国管理局へ提出します。そこには(3)でみた労働条件等を記載している必要があります。(雇用契約書のサンプル)その場合、在留資格がまだ許可されておらず、働けるかどうかがわかりませんので、「本契約は日本政府による就労可能な在留資格の許可または在留期間の更新を条件として発効する」といった停止条件をつけておくことが一般的です。
(5)会社の経営状態
採用する外国人を安定的に雇用するために、雇用主の経営が安定していることが求められます。経営状態は、原則は決算書、場合により試算表、事業計画書、契約書などが審査されます。
なお、企業は、その企業規模等に応じて、カテゴリー1から4までに区分されています。カテゴリー1は上場会社、カテゴリー2は人件費を概ね年間1億円以上くらい支払う未上場企業、カテゴリー3はそれ以外の中小事業者、カテゴリー4が新設会社のイメージです。カテゴリー区分によって求められる資料や審査期間が異なります。

カテゴリー3の中小企業で、売上高が小さかったり、直近の決算が赤字または債務超過の場合は、雇用の安定性に疑義が生じるとして審査が厳しくなります。その場合、一般的には事業計画書やその他のエビデンスから経営状態について説明をします行います。
また、新しく立ち上げた会社の場合は、決算をまだ行っていないので、事業計画書の提出が必須となります。各カテゴリーで入国管理局の必要資料が異なります。
(6)外国人の素行が良いこと(前科や法令違反がないこと)
外国人本人の素行が善良であることが在留資格許可の前提となります。本国で重大な犯罪を犯していたり、国内で犯罪行為を犯していないこと、入管法その他の法令を遵守していることです。例えば、留学生は、アルバイトの就労時間制限(週28時間)の遵守などには注意が必要です。また、離婚した場合、転職をした場合などの入管法上の届出義務を履行していることが確認されます。元技能実習生は、技能実習法の目的や過去の入管当局への申告内容が問題になりえます。
外国人の雇用主企業等の注意点!
日本では外国人の不法就労は法律(入管法73条の2)で禁止されています。不法就労は、外国人だけでなく、不法就労させた事業主も不法就労助長罪という罪で処罰の対象となります。また、申請人外国人が虚偽の申請をしたと認められる場合、在留資格等不正取得罪(入管法70条1項)として、3年以下の懲役・禁固若しくは3百万円以下の罰金、又はそれらが併科される場合があります。雇用主は「周りもやっているから大丈夫」など、安易な気持ちで不法就労や虚偽申請とならないよう注意してください。
また、外国人スタッフ採用後の各種手続きも忘れないようにしてください。
人事担当者の方へ
技術・人文知識・国際業務ビザを活用することで、専門的な知識を持つ外国人をスムーズに採用することが可能です。コンチネンタルでは、外国人ビザに関するコンサルティングを提供しており、在留資格申請のサポートや、ビザ取得手続きの代行も行っています。オンラインでの在留資格申請やCOE・在留カードの受領も代わりに行うことができます。対象者や外国のHR担当の方へ直接ご説明することも可能です(英語のみ)。

お問い合わせ先:
Continental Immigration & Consulting
東京都港区赤坂 2-16-6
電話番号:03-6403-9897
また、修士以上の学位を持つ方や見込み年収が1000万円を超える予定のかたなど「高度専門職」の在留資格に該当する場合は、高度専門職をお勧めすることがあります。詳細については、お気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
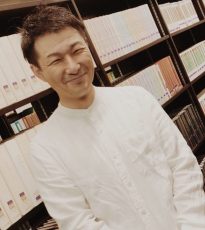
村井将一(むらい まさかず)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、労務環境改善活動に従事。
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
入国管理局申請取次行政書士、東京都行政書士会 港支部 執行役員
CFP(Certified Financial Planner)
日本証券アナリスト協会検定会員