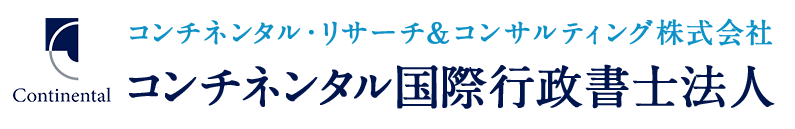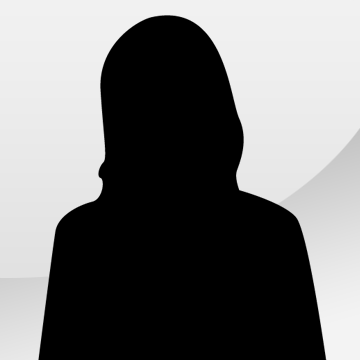行政書士として見えてきた“共鳴の実例”
行政書士として見えてきた“共鳴の実例”
高度人材・ホワイトカラーが集まる事務所は何をしているのか?
コンチネンタル国際行政書士法人では、創業当初から一貫して「高度人材」と呼ばれる外国人の方々からのご依頼が多数を占めています。高度人材とは、入管法で定める高度人材ポイント計算表で高度専門職の在留資格を取得できる属性の人を指します。
高度人材ポイントシステムは、学位、出身大学、職歴、年収、年齢、日本語能力、保有している資格、学術論文、勤務先などにポイントが付与されており合計70点以上が高度専門職の在留資格に該当する可能性があるものです。
例えば、日本の国立大学で修士の学位を取り、日本語N1を持つ30歳で、外資系企業で勤務歴4年目、年収1200万円で勤務する外国人の場合、学位20点、出身大学10点、職歴5点、年収40点、年齢10点、日本語15点で合計100点になります。
具体的には、修士号以上の学位を持つITエンジニア、博士号を持つ国際機関に勤務する専門職、ニューヨーク州などの外国弁護士資格を持つ人、米国の名門大学(GSやTHEのワールドユニバーシティランキングの100位以内など)の出身者、医師など概ね高度専門職の基準に該当します。



他方で、当法人では、SNSや広告を通じたターゲティングを行ったわけではありません。それにもかかわらず、彼らが自然と事務所にたどり着き、問い合わせから相談、そして依頼へと進んでくださるのです。
この事実を当初は偶然と考えていましたが、複数年にわたる顧客データと日々のコミュニケーションを振り返るうちに、ある傾向が浮かび上がってきました。それが「共鳴する周波数」という考え方です。私たちが提供する情報、話し方、サイトデザイン、文章のトーン——そのすべてが、結果的に高度人材の文化資本と自然に合致していたのです。
彼らは価格ではなく、信頼と安心を重視します。だからこそ、見た感じがまともで、情報が体系的に整理され、専門性が伝わるデザインに反応します。そして何より、「この先生なら、自分の話をきちんと理解し、法的に信頼できる対応をしてくれる」という確信が、彼らの選択を後押ししているのです。
なぜ技能実習生や価格比較客は来ないのか?
一方で、技能実習生・特定技能外国人のご本人またはその雇用主・配偶者、あるいはインターネットで価格を比較してから相談してくる顧客層は、当法人にはほとんど訪れてはくれません。それは決して排他的なスタンスを取っているからではなく、むしろ「周波数が合っていない」ことが理由であると考えています。
たまにご連絡をいただいた際にお聞きすると、彼らが求めているのは、「誰に依頼しても結果が同じなので」「いかに安く」「いかに簡単に」「手続きを代行してもらえるか」です。または、本当に悪意無く「無料で話だけ聞きたい」「費用が掛かるならば自分で手続きをやってしまいたいので、心配なところだけタダで聞きたい」というものです。
その背景は以下の外部要因によるところと、内部要因によるものに大別されます。
外部要因によるもの
米国・カナダ・英仏独などG7諸国では、母国にもイミグレーションロイヤーが存在し、ビザ手続きを行うときにはそのロイヤーに安くない報酬を支払うことが一般的です。不法移民などを防ぐ目的で厳しいビザ審査があるからです。
他方で、それ以外の国では、母国でイミグレーションロイヤーを雇ってビザ申請することが一般的ではないことも多く、高い報酬を払ってロイヤーに相談をするという文化もないことも多いようです。悪気なしに専門家に「無料で話だけ聞きにきました」という趣旨のことを平然と言ってしまう、当初からボタンの掛け違いが発生することがあるのはこのせいでしょう。
ちなみに、日本人からの相談もこのケースが多いです。日本人で「費用が掛かるならば自分で手続きをやってしまいたいので、心配なところだけタダで聞きたい」と専門家に率直に言ってしまう背景は、日本にも古来からイミグレーションロイヤーの文化が無いことや、相談者がいわゆるコンサルティング業のような役務提供を対価として報酬を得る仕事をしたことがない、又は民間企業での営業経験などがないことなどが原因だと考えられます。*当然に市役所の無料相談会のノリでご本人には悪気がありません。
内部要因によるもの ~心理学者アルヴィン・トフラー(1970)など
入管法にかかわらず(税務でも労務でも)、制度上、複雑な仕組みや多くの論点があるため、専門家としてはリスク説明をする必要があります。証券会社では投資した商品のリスクを十分に説明しますし、外科手術でも万が一に失敗するリスクについて説明され、そのことについての承諾書を差し入れることも一般的です。そこで、当法人では予め法令や手続きのリスク情報をできる限りわかりやすく説明するようにしていました。
しかし、心理学者アルヴィン・トフラーが1970年に提唱した情報過多ストレス(Information Overload)では、「情報の爆発的増加は、人間の意思決定や心理に悪影響を及ぼす」とし、近年でもダニエル・カーネマンの「ファスト&スロー(2011)」の理論でも、情報過多の中で人は(直感・感情)に頼る傾向があるとされています。
つまり、一般的に人間は、「情報が多すぎて処理できない」と感じたとき、論理ではなく感情や見た目、印象といった“表面的な判断軸”にスイッチしてしまうということです。これは書類の分量や説明文の密度が高すぎると、顧客が「感覚的に嫌になる」原因になります。
他方で、Petty & Cacioppoの「精緻化見込みモデル(ELM: Elaboration Likelihood Model、1986)では、教育水準が高い人ほど、詳細な説明・根拠・手続きの背景などを求める傾向があり、「細かすぎる説明は嫌われる」という一般論が必ずしも当てはまらない層と言えるとしています。
当法人では、料金表を明示し、複雑な要件を丁寧に説明し、信頼性と専門性を前面に出すことで、相手に選んでもらうという設計を意識しています。結果として、「安さ」や「スピード」を最重視する層と自然とすれ違う構造ができあがっていました。
排除ではなく“選ばれる設計”としての周波数理論
誤解のないように申し上げると、この事例はレアかもしれませんが、「誰かを排除するためのブランディング」ではありません。むしろ、すべての発信は「誰に見つけてもらいたいか」という設計思想の延長線上にあります。私たち士業や専門家はあくまで「選ばれる存在」であることを目指しています。
そのためには、見た目の印象、文章の文体、図解の使い方、声のトーン、受け答えの丁寧さ、先生のキャラクター、事務所の世界観すべてが“周波数”の一部となります。そして、それらが一貫しているからこそ、共鳴する顧客が「この先生に、この事務所にお願いしたい」と自然に思えるのです。
逆に言えば、周波数が混線している事務所、つまりメッセージやビジュアルに一貫性がない場合、顧客は「なんとなく違和感がある」と感じて離れてしまいます。そこで価格競争に走れば、今度は「より安いところ」に顧客を奪われてしまうだけです。
昨今のSNSを頑張ろう!SEOを頑張ろう!LINE対応必須!子供でもわかるように簡単に!という風潮と、先生のキャラや事務所の世界観が相違している場合、流行りの格安居酒屋チェーンのように差別化できず埋もれてしまいますし、おぢが金髪にて若者に流行りの洋服を着ているようにチグハグに見えるのかもしれません。先生の個性、事務所の世界観に合ったお客様を探してみてはどうでしょうか?YouTubeの世界でも一緒です。例えば、イケメン男子、美女のフォロワー50万人のインフルエンサーと高橋洋一さんや玉木雄一郎さんは視聴者層が違います。
それぞれの先生に、それぞれの共鳴がある
ここで重要なのは、「万人に共鳴する周波数など存在しない」という事実です。行政書士として独立した当初は、つい「どんな案件でも取りたい」「誰からでも相談されたい」と思いがちでした。しかし、すべての人に好かれようとすると、結果的に誰にも響かなくなってしまいます。
私は、高度人材と共鳴しましたが、別の先生は、地域密着の行政手続きに特化し、高齢者からの絶大な信頼を得ているかもしれません。また、外国人技能実習生や難民申請者支援に特化して、現地語対応で確かなニーズを掴んでいる先生もいます。
それぞれの先生が、自分自身の文化資本や価値観、人生経験をもとにした発信をすれば、それに共鳴する顧客が必ず現れます。そして、その顧客こそが、長く信頼関係を築き、紹介やリピートへとつながる最良の顧客となるのです。
次に、自分が共鳴すべき相手をどう見つけ、そのための発信をどう組み立てていくかについて、さらに実践的な視点から掘り下げていきます。
記事(全10回)
- なぜ、あなたのところに“あの顧客”が来るのか?
- “周波数”とは何か?──顧客が共鳴する見えない力
- なぜ周波数が一致するのか──文化資本と世界観の一致
- 行政書士として見えてきた“共鳴の実例”
- すべての士業にある“におい”──見えないブランディング
- 誰と共鳴したいか?──顧客設計と自己理解
- 自分の周波数を可視化するワーク
- 士業の集客を“戦術”から“世界観”へシフトする
- 誰もが「響き合う場」をつくれる──多様性のマーケティング
- 周波数を信じて立つ──営業しなくても選ばれる存在へ
この記事を書いた人
 村井将一(むらい まさかず)
村井将一(むらい まさかず)
コンチネンタル国際行政書士法人 代表社員 マネージング・ディレクター
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米モルガン・スタンレーとのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に従事。
在職中、現場業務に従事しながら従業員組合中央執行委員として職場内の外国人や女性の活躍などのダイバシティ推進、セクハラ・パワハラ・過剰残業対策など労務環境改善活動に従事。専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。
行政書士 東京都行政書士会港支部 副支部長
日本証券アナリスト協会検定会員
CFP(Certified Financial Planner)