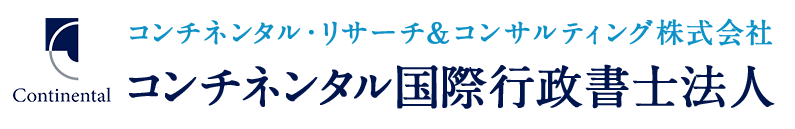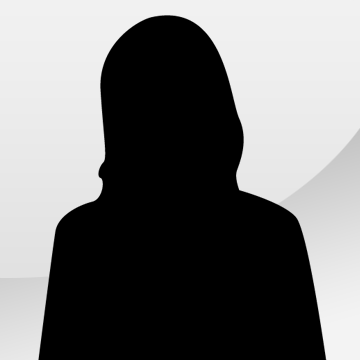共鳴する顧客像を見つけるワーク──“誰に見つかりたいか”を設計する
共鳴する顧客像を見つけるワーク──“誰に見つかりたいか”を設計する
ここまでで、「誰からも選ばれたい」という発想から脱却し、「誰に共鳴するか」を起点にした設計思想が重要であることを述べてきました。今回は、あなた自身が共鳴すべき顧客像をどう見つけ、そのための“周波数の整え方”をワーク形式で掘り下げていきます。
自分の発信に“反応する人”を探す
まず第一に考えるべきは、「どんな人があなたの言葉やスタイルに反応したか」という過去の実績です。これは分析ではなく“観察”から始まります。
<ワーク①:共鳴ログを作る>
- 過去1年間の問い合わせや相談の中で「この人とは話が通じやすかった」と感じた事例を5件以上書き出してみましょう。
- 次に、相談者の属性(年齢・性別・職業・学歴・国籍など)を記録します。
- 最後に、「何をきっかけに自分を見つけたのか(HP、SNS、紹介など)」も合わせて整理してみてください。
たったこれだけでも、ある一定の傾向が浮かび上がることが多くあります。 たとえば、「全員が40代以上の女性だった」「みんな最初にサービスページではなくコラムを読んでいた」などの共通項が見えてくるはずです。
顧客の“周波数”を言語化する
共鳴している顧客像が見えたら、その人たちの価値観や情報処理スタイルを整理しましょう。
ここはマーケティングでよく出てくるペルソナです。
<ワーク②:顧客ペルソナを立てる>
例)
名前:ジョナサン(仮)
年齢:35歳、英国出身、修士号保持
職業:日本の外資系企業でAI関連のプロジェクトマネージャー
情報収集のクセ:日本語も読めるが、英語併記を好む。要件定義やフロー図が好き。
好まれるトーン:感情的な共感よりも論理的な正確性を重視
このように、単なる属性ではなく「どういう言葉に共鳴し、何に信頼を寄せるか」まで言語化することで、周波数の設計が明確になります。
自分の文化資本を顧客の“受信機”に合わせる
第2話で述べた文化資本(身体化・客体化・制度化)を、理想の顧客に合った形で“表現”していく必要があります。
たとえば、学歴や職歴を「書く」ことに躊躇する先生も多いのですが、高度人材にとっては「誰に頼むか」を選ぶ重要な判断材料になります。制度化された文化資本を隠すのではなく、丁寧に提示すれば、それだけで大きな共鳴が生まれます。
同様に、文章表現も身体化された文化資本の現れです。ですから、普段から読む書籍、好む言い回し、専門用語の選び方なども「周波数」として受信されているのだと意識してください。
<ワーク③:文化資本の棚卸し>
- 学歴・資格・職歴を一覧化(制度化)
- よく使う表現・語彙のパターンを記録(身体化)
- サイトや資料、動画などのビジュアル要素を点検(客体化)
顧客が“見つけやすい場所”を選ぶ
たとえ顧客像と文化資本が一致していても、発信の“場”がズレていれば出会うことはありません。
SNS? note? 自社サイト?
- 高度人材層は、noteのようなオピニオン型媒体や英語併記された自社サイトを好む傾向があります。
- 一方、安価なサービスを求めるライト層は、X(旧Twitter)やLINE、Google検索で簡潔な情報を拾う傾向にあります。
<ワーク④:メディアマッピング>
理想の顧客が使っている/共鳴しやすいメディアを●で囲み、自分の発信メディアと重なっているかを確認しましょう。
例:
note ●
│
自社サイト ●───SNS(Instagram)
│
X(旧Twitter)
このマッピングで、「どこで発信すれば届きやすいか」が視覚的に見えてきます。
“自分を見つけてくれる人”を信じる
最後に忘れてはならないのは、「万人に届ける発信」ではなく、「自分を見つけてくれる人を信じる発信」に切り替えることです。反応が少なくても、それは共鳴する層だけが残ってくれている証拠です。 ターゲットを絞ることは、誰かを拒絶することではなく、「響く相手に真っすぐ届ける行為」なのです。次回は、こうした設計を実際の発信にどう落とし込むか──文章やデザイン、導線の実践例を詳しく紹介していきます。
記事(全10回)
- なぜ、あなたのところに“あの顧客”が来るのか?
- “周波数”とは何か?──顧客が共鳴する見えない力
- なぜ周波数が一致するのか──文化資本と世界観の一致
- 行政書士として見えてきた“共鳴の実例”
- すべての士業にある“におい”──見えないブランディング
- 誰と共鳴したいか?──顧客設計と自己理解
- 自分の周波数を可視化するワーク
- 士業の集客を“戦術”から“世界観”へシフトする
- 誰もが「響き合う場」をつくれる──多様性のマーケティング
- 周波数を信じて立つ──営業しなくても選ばれる存在へ