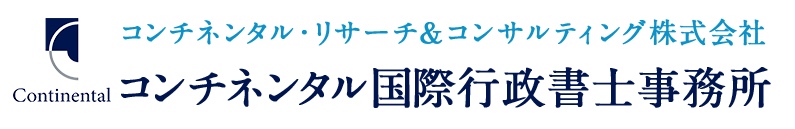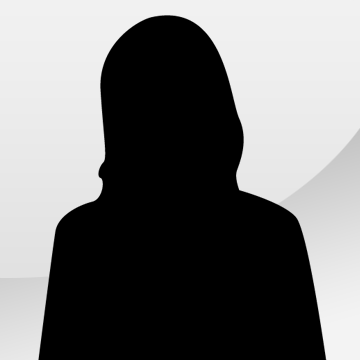技能実習制度にみる特定技能の課題
技能実習制度にみる特定技能の課題(UPDATED)
技能実習生の日本での労働環境・待遇の悪さが多く指摘され、問題となっていることは周知の通りです。
主に外国のブローカーや送出機関に払うお金を借金してから日本に来ていることが指摘されていますが、大きな原因の一つは、日本で監理団体へ毎月支払うお金が必要などの技能実習の構造上の問題であると筆者は考えています。技能実習生を受け入れる(実習実施=雇う)企業等は、月々おおよそ4-5万円程度の費用を監理団体等に支払います。技能実習生と雇用契約を結び、福利厚生や労働法上の残業や有給その他の扱いは日本人労働者と同じくなるはずとされています。
もしも、月給が日本人の労働者と同額であれば、監理団体に支払う月額の費用の分だけ、企業側は雇用コストが高くなります。さらに外国人本人の母国との往復渡航費用の負担や面談する際の採用コストもあります。それらを吸収するために(=雇用にかかる費用を日本人の採用時と同等以下にするために)、実習生本人の月々の給料は日本人よりも安く抑えられ、最低賃金に近い水準になることが多くあります。
技能実習の対象職種は、日本人であっても賃金の低い所謂単純労働とみなされる職種が多く、それらの職種の事業者は、低い労働コストによって事業が成り立っているため、もともと低い賃金水準から更に監理団体等のコストが差し引いた極めて低い賃金水準が実習生らの手元に行くことになります。
これを「特定技能」に置き換えると、特定技能では、外国人労働者の賃金は、他の就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務など)と同じく、日本人と同等額以上を求めています。最低賃金のような水準で支給することはできません。他方で、受け入れる企業には、特定技能外国人の母国語での生活支援などが細かく求められています。自前で外国人労働者の支援ができない場合は、登録支援機関への委託が求められています。
つまり、外国人支援体制を構築する管理部門コストや登録支援機関への委託費用などが発生する一方で、日本人と同じ給料コストが発生するため、その分だけ雇用コストが割高になります。
特定技能の対象職種として認められた業種は、前述の技能実習の場合のように、労働集約的な単純労働が多く、IT化やロボット化が難しい業種でもあります。
そして、制度上、技能実習のように外国人労働者を低賃金で扱うことでのしわ寄せががルール上できなくなるため、企業の利益の確保は今よりも難しくなります。したがって、特定技能を利用する企業側に特定技能外国人で雇用できるだけの体力(=高い雇用コストを支払っても、なお人員確保により利益の出ること)があるか否かがポイントになります。
対象業種の中には、建設業や一部製造業など比較的業務粗利額の高い業種もあり、日本人を雇用するよりも高い雇用コストであっても経済合理性を維持できる業種もあると思いますが、介護やビルクリーニングなど構造的に賃金を低く抑えなけば成立しないビジネスモデルの場合では、特定技能の在留資格が機能するかどうか懐疑的です。
コンチネンタルでは、上記のような理由から2019年に導入された特定技能の導入が今一つ進まないものと思料しています。マスコミでは、制度が複雑、申請準備が大変、試験の実施が限定的、などが導入の進まない理由とされて報道されることが多いですが、これらは本質的な問題ではありません。
なぜならば、企業がカネを払い管理部門スタッフを拡充する、外部の専門家などに完全にアウトソーシングすることができれば解決するからです。したがって、当社では、試験合格者が増え、COVID19による渡航制限が緩和されたとしても、導入の進み具合は緩やか/限定的であると予想しています。
メディア取材・執筆のご依頼はこちらまで
info@continental-immigration.com
この記事を書いた人
 村井将一(むらい まさかず)
村井将一(むらい まさかず)
1977年生まれ。三菱UFJモルガン・スタンレー証券(三菱UFJフィナンシャルグループと米Morgan Stanleyのジョイントベンチャー)で企業の資金調達やM&Aなどのアドバイスを行う投資銀行業務に18年間従事。在職中500人を超える起業家や上場企業経営者に対して事業計画や資本政策などの財務・資本戦略についての助言を実施
専門は外国人の在留資格手続きに関わるコンサルティング及び財務コンサルティング。趣味は日本人アイドルのコンサートとディカプリオ映画と猫と遊ぶこと。
入国管理局申請取次行政書士・CFP(Certified Financial Planner)・日本証券アナリスト協会検定会員
相談してみる
【外国人のみなさま】
◆ 日本で働きたい
◆ 日本で会社を作りたい
◆ 結婚したい
◆ 永住したい
◆ 日本国籍をとりたい
【事業主のみなさま】
◆ 外国人を雇いたい
◆ 入国管理局への申請をしてほしい
コンチネンタ
 ルLINE@ではホームページには書いていないニュースやBlogを配信しています。この機会に是非友達追加を!!もちろんLINE@からのご依頼もOKです!
ルLINE@ではホームページには書いていないニュースやBlogを配信しています。この機会に是非友達追加を!!もちろんLINE@からのご依頼もOKです!